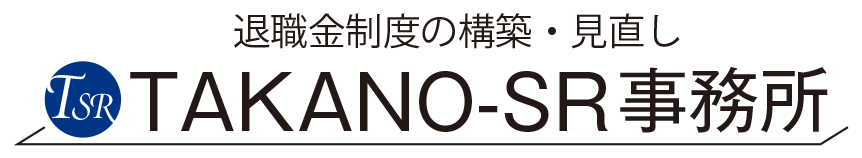退職金の算定方法
退職金額の算定は、退職金規定等に定められた計算方法等に基づいて行われます。
基準額、勤続年数、係数等を用いて退職金の支給額計算する方法以外にも 毎月拠出する金額(掛金額)を定める方法、積立てるべき退職金の原資を賃金で支払う方法「退職金前払い制度」もあります。
基本給連動型
退職時の基本給をベースとして、勤続年数、退職事由などの要素を勘案して計算する方法。
勤続年数が長く優秀な従業員は基本給が高くなるので、退職金額が多くなります。
(退職金の計算式)
退職時の基本給×支給率(勤続年数による)×退職事由による係数
<メリット>
・計算や管理が比較的容易
<デメリット>
・退職時の基本給をベースにしているため、各個人の基本給の予測がしづらい。
・退職金額が高額になるケースがある。
・勤続年数が長いほど退職金が高くなるので、貢献度が評価されにくい。
・基本給の見直しを伴う給与制度変更がしづらい。
定額制
会社が定めた基本額に勤続年数を乗じて支給金額を決める方法。
勤務年数で退職金額が決定される。
(退職金の計算式)
基本額(基本給、役職等に関係なく一律で定める金額)×勤務年数
<メリット>
・計算方法が簡単
・退職金額の把握や将来の予測が可能
・給与制度を変更しても退職金制度に影響しない
<デメリット>
・在職年数が長いほど退職金が上がる仕組みなので、中途採用者は不利
・在職中の貢献度は反映されない
別テーブル型
給与制度とは別建てに設定した基本額に退職時の等級ごとの係数を乗じて 計算する方法。
(退職金の計算式)
基本額(勤務年数、退職事由等によって定める)×退職時の等級別係数
<メリット>
・給与制度を変更しても退職金制度に影響しない
・退職金額の計算や将来の額の予測が比較的容易
<デメリット>
・退職金の計算になる基礎が勤続年数、退職事由、退職時の等級に限定されるため、在職期間全体の評価が反映されない
ポイント制
従業員の1年ごとにポイント(勤続ポイントと職能ポイントの合計等)を付与し、その累計ポイントに会社が決めたポイント単価を乗じて支給金額を決めます。
(退職金の計算式)
累計退職金ポイント×ポイント単価×退職事由による係数
<メリット>
・在職中の貢献度が反映させることができるので、モチベーションアップにつなげることができるが、退職金額がばらつくことがある
・中途採用者でも貢献度が高ければ退職金額を上げることが可能で、優秀人材の獲得と流出防止につながる
<デメリット>
・ポイント制を運用する場合は、人事考課基準を定め、正しく運用することが必要であり、適切な運用が難しい
・1年ごとの業績を査定する必要があり、管理事務が煩雑になる
退職金算定方法は、どの方法が優れていてどの方法が悪いというものではありません。
その企業が 実態に合わせて適切に設定・運用をすれば 十分に機能しますし、適切でなければ 機能しません。
各企業が考える「退職金の意義」に合う算定方法を適切な設定・運用により使いこなすことが一番です。